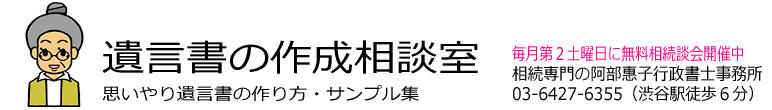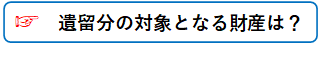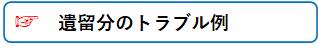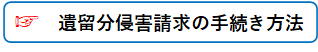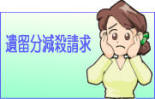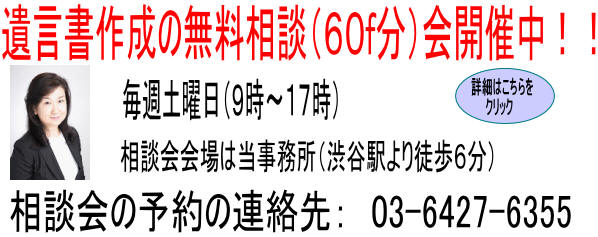遺留分とは
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続できる財産の最低保証割合の事です。
生前贈与や遺言によって特定の相続人に多くの財産を相続させたり、法定相続人以外の人に贈与がや遺贈した場合に、遺留分割合を下回った場合に遺留分侵害が発生します。
遺留分権者と遺留分割合
1)遺留分権者ととは
遺留分の権利者とは下記のとおり兄弟姉妹以外の法定相続人です。
①配偶者
②子供・亡くなっている場合は孫(代襲相続人)
③直系尊属(父母または祖父母)
*法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。
胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。
また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方、欠格、廃除の方は対象外です。
2)相続財産に対する遺留分の割合
①相続人が配偶者や子供、または相続人が配偶者と直系尊属など の場合
⇒ 法定相続分の1/2
②直系尊属のみが相続人である場合
⇒ 法定相続分の1/3
遺留分侵害額請求の期限は
遺留分侵害額請求の消滅時効は遺留分権利者が相続の開始及び侵害額請求すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または知らなかったときでも相続開始から10年です。
消滅時効を避けるには内容証明郵便で意思表示をしておく必要があります。相手への内容証明の送付により消滅時効が中断します。